バイクのウインカー交換は自分でできる?やり方解説!
保安部品であるとともに、見た目にも影響するバイクのウインカー。
故障して交換が必要になったり、LEDにして明るくしたいと思うこともあるのではないでしょうか。
ウインカーの交換について考えると、「バイクショップに依頼すると費用が高そう」「自分でもできるのだろうか」と感じる方もいるかもしれません。
そこで今回は、バイクのウインカー交換のやり方を分かりやすく解説します。
ウインカーを交換してかっこよくしたい方や、故障などでウインカー交換が必要な方は、ぜひ最後まで読んでいってくださいね。
目次
手順①:必要な工具をそろえる
ここでは、ウインカー交換に必要な道具をそろえることについて紹介します。
工具をそろえてから作業する
ウインカー交換は、ネイキッドタイプのバイクであれば比較的簡単に交換できますが、スポーツバイクやフルカウルのバイクは少し難しいです。
適当な工具で取り外してしまうと壊したり、バイクに傷を付けてしまうことがあるため、基本的な工具はそろえておきましょう。
ドライバー
まず最初に使う工具がドライバーです。
ネイキッドタイプのバイクはヘッドライトを取り外す必要があり、ヘッドライト本体下部のネジを外してヘッドライトレンズを取り外します。
ネジのサイズは複数あるため、3種類程度の大きさのドライバーをそろえておくと、幅広く対応できて便利です。
スパナやメガネレンチ
スパナやメガネレンチはウインカーの固定部分を緩めるために使用します。
ウインカーの根元部分は、裏からナットで固定されている場合が多いです。
また、ウインカーの配線を通すためにナットの中央に配線が通っている場合があります。
このような場合、メガネレンチは使用できないので、スパナを使用するようにしましょう。
ナットのサイズはバイクによって異なりますが、12~17mm程度のサイズが一般的です。
自分のバイクのナットのサイズをあらかじめ確認して、適切なサイズのスパナやメガネレンチを用意しておきましょう。
電工ペンチ
電工ペンチは、配線同士をつなぐためのギボシ端子を作成する際に使用します。
ウインカーには、最初からギボシ加工がされているものもありますが、加工されていない配線のみの場合もあります。
そのため、ギボシ端子を作成することを想定して、電工ペンチを用意しておきましょう。
このように、ドライバー・スパナ・電工ペンチがあれば基本的にウインカーの交換が可能です。
ウインカーは保安基準で定められている重要な部品なので、確実かつ丁寧に作業することが大切です。
手順②:元々ついているウインカーを外す
ウインカーの配線を丁寧に外す
まずは、既存のウインカーの配線を外します。
純正ウインカーであればカプラー接続になっていることが多く、プラスマイナスを意識せず簡単に取り外せる場合があります。
そうでない場合は配線の色やプラスマイナスを間違えないように、紙にメモしたり写真を撮ったりして記録しておきましょう。
配線を雑に扱うとカプラーやギボシを破損する恐れがあるため、慎重に進めてください。
ウインカーの根元を緩めて外す
ウインカーの裏を見ると、ナットやボルトで固定されています。
これらをスパナやメガネレンチを使って緩め、ウインカーを外しましょう。
ウインカーの根元には振動を抑えるゴムがありますが、これが緩める際に邪魔をして供回りしてしまうことがあります。
そのため、ウインカーの根元のナットやボルトを緩めるときは、ウインカー本体が回らないようにしっかりと持って緩めましょう。
ウインカーは全部外さない
ウインカー交換は最大で4個ありますが、1個ずつ交換することをオススメします。
すべてのウインカーを一度に外してしまうと、配線が分からなくなった際に参考にできるものがなくなるためです。
左右のウインカーを同時に外すと、どちらが右のウインカーで、どちらが左のウインカーの配線か分からなくなる可能性があるので、1か所ずつ交換していきましょう。
手順③:新しいウインカーをつける
新しいウインカーの内容を確認する
新しいウインカーは純正品であればそのまま取り付けるだけですが、社外品のウインカーキットを使用する場合は、ウインカーステー、配線、ウインカーがバラバラになっていることがあります。
そのため、説明書を見ながら内容物を確認する必要があります。
ウインカーは保安基準や車検でチェックされる重要な部品ですので、必ず確認して確実に取り付けましょう。
ウインカーを組み立てる
バラバラになっているウインカーを確認した後は、組み立てを始めます。
ウインカー本体から配線が出ているので、まずはウインカーステーにこれを通し、ウインカー本体と組み合わせてください。
次に、ウインカーにウインカー球を取り付けます。
ウインカーには左右共通のものと左右専用のものがあるため、説明書やウインカー本体を確認しながら、間違いのないよう正確に組み立てましょう。
ウインカーをバイクに取り付ける
ウインカーが組み立てられたら、元々ウインカーが付いていた穴を利用して新しいウインカーを取り付けましょう。
まず、配線を通し、次にウインカーステーを取り付けます。
その後、ワッシャーやナットを裏から通して締め付けていきます。
ナットを締める際、最初は工具を使わず手で締め込むのがオススメです。
工具を最初から使用すると、ナットが斜めに入ってしまった際、気付かずにステーのネジ山を破損するリスクがあります。
ウインカーの角度を決めて工具で締め付ける
ウインカーを工具で締め付けていきます。
締めつけるとウインカーが供回りし始めるため、手で固定しながら締め付けましょう。
ウインカーの角度は純正品なら固定されていますが、社外品の場合は自由に角度を変更できます。
基準としては地面と平行に取り付けることをオススメします。
ウインカーの角度を決めたら、手で固定し、しっかりと締め付けましょう。
手順④:配線を繋いでまとめる・配線カバーをつける
配線を繋ぐ
ウインカーの取り付けが終わったら、次に配線を接続します。
配線の先端はギボシ加工されたものと未加工のものがあります。
加工済みの配線であれば、そのまま取り付けていきます。
一方、バイク側がカプラーのままの場合が多いです。
バイクのカプラーを切らずにアダプターを購入することで、カプラーからギボシへ変換することができます。
オスとメスがギボシになったら、配線の色や説明書を参考にして、プラスとマイナスを間違えないように取り付けましょう。
ウインカーの配線をまとめる、カバーを付ける
ウインカーの配線を接続したら、次に配線をまとめましょう。
ネイキッドタイプのバイクの場合、ウインカーの配線は通常ヘッドライト内に収納されます。
配線は元々のウインカーの配線が収まっていた場所に沿って収納すれば、ヘッドライトを取り付けたときに配線が潰れる心配はありません。
ウインカーのキットによっては、ウインカー固定部分から出る配線のカバーが付属していることもあるので、その場合は取り付けましょう。
また、ヘッドライト内の配線にもカバーを取り付けることで、ショートや水濡れを防ぎます。
手順⑤:ウインカーをつけて状態を確認する
ウインカーの点灯確認をする
ウインカーを取り付けた後は、実際に点灯させて確認しましょう。
ウインカーの接続を左右で間違えると、前は右が、後ろは左が点灯するようなちぐはぐな点灯になってしまうので、必ず確認が必要です。
また、プラスとマイナスを間違えると点灯せず、ヒューズが切れる場合もあるので注意しましょう。
点滅の速度が速い
ウインカーを点灯させた際に非常に早い間隔で点滅することがあります。
この現象はハイフラッシュと呼ばれ、ウインカーのワット数が合わないためにウインカーが早く点滅してしまう現象です。
これはウインカーのワット数が純正のものよりも低くなってしまい、ウインカーリレーが対応できずに早く点滅してしまうためです。
ハイフラッシュ現象を抑えるためには、どのようなワット数にも対応できるLED対応ウインカーリレーを購入して交換することをオススメします。
LEDに交換したときにも注意する
ウインカーを交換する際、ワット数を変更する場合でもハイフラッシュ現象が発生します。
ウインカーの点滅規定は1分間に60回以上120回以下ですが、これはLEDに交換した際に最も起こりやすい現象です。
ハイフラッシュ現象は目立つため、整備不良とみなされ警察に止められることがあります。
LED電球に交換する際は、この現象に十分注意し、ハイフラッシュ現象で取り締まられないようにしましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回はバイクのウインカー交換の方法を紹介しました。
バイクのウインカー交換は、壊れてしまった場合や、社外品やLEDウインカーへのカスタムが一般的です。
ウインカーの交換はバイクショップに依頼することもできますが、自分で交換してみたいと思う方も多いのではないでしょうか。
バイクのウインカー交換は比較的簡単ですが、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
今回紹介したウインカー交換の方法や注意点を参考に、自分のバイクのウインカーをかっこよくカスタムしてみてください。
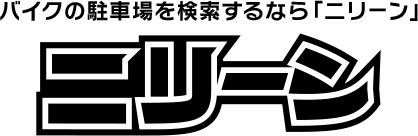

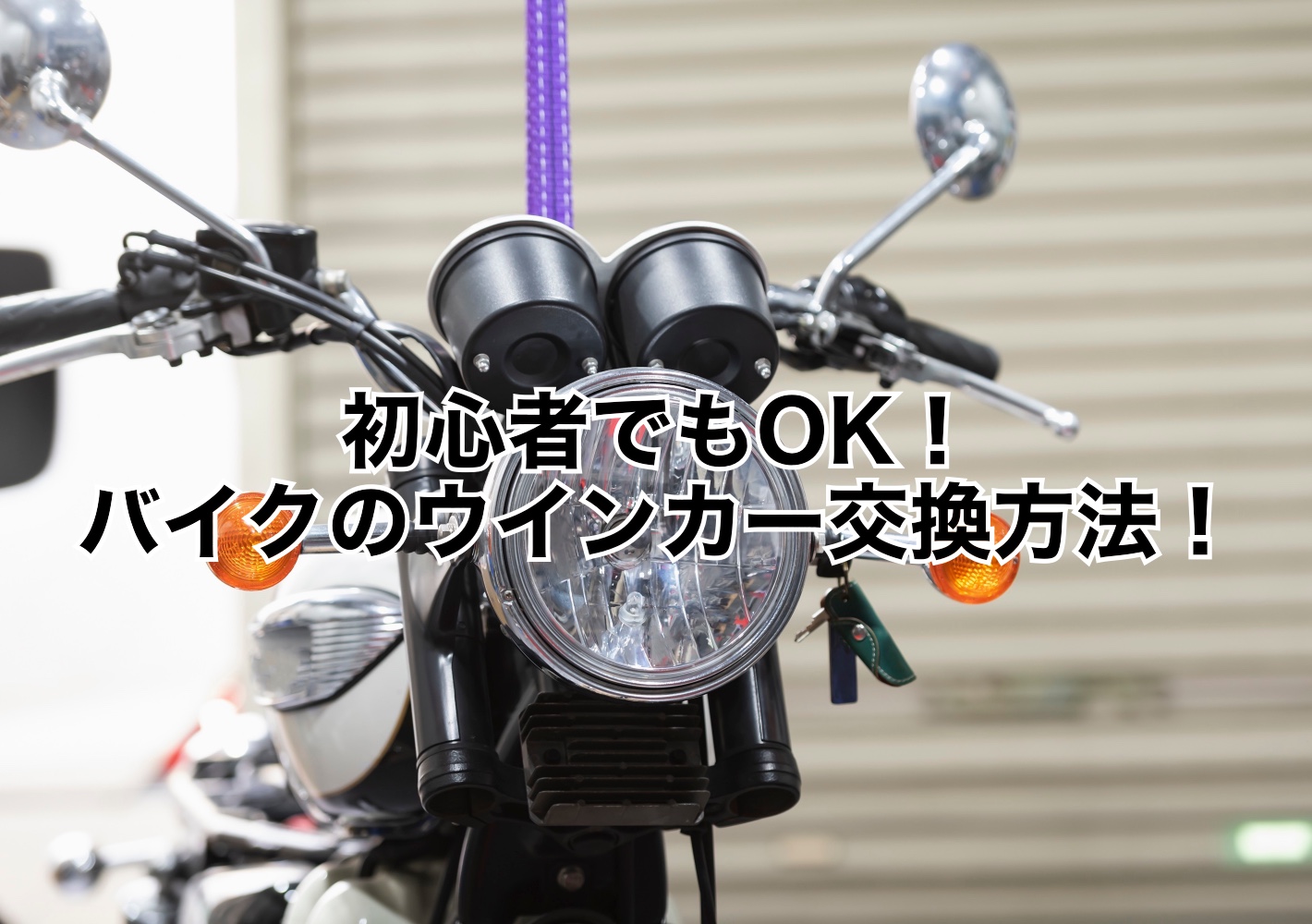
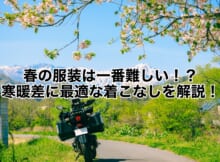


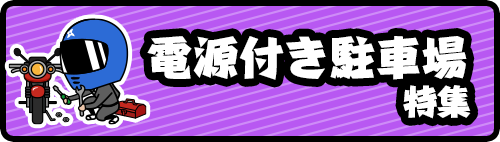
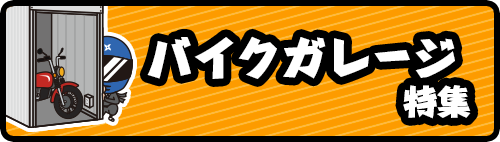
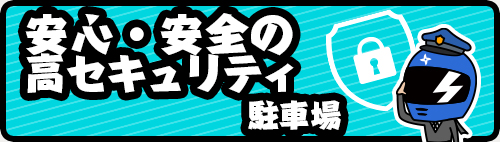
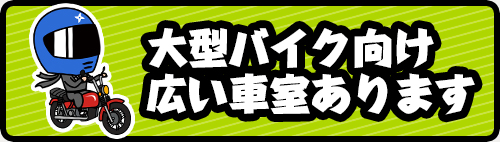
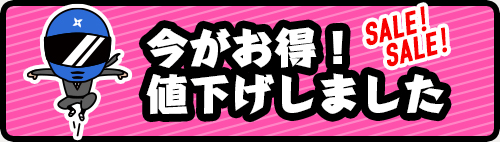

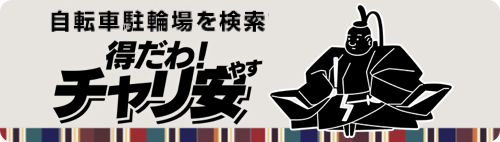

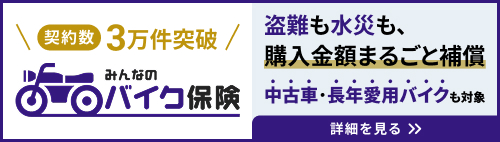

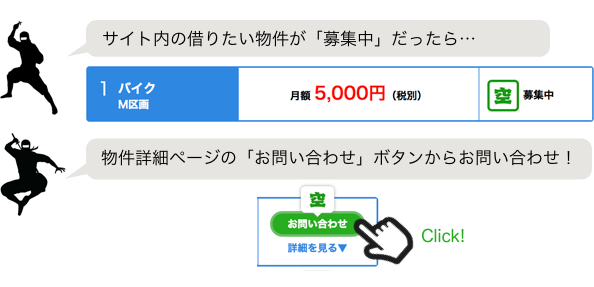
.jpg)