「クラッチが思うように切れない」「半クラが決まらない」をクラッチ調整で解決!
バイクの運転において重要なクラッチレバー。
長く乗っていると、「以前は思い通りに切れていたのに、最近切りづらくなった」と思うこともありますよね。
しかし、「クラッチ調整のやり方が分からない」という方も意外と多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ワイヤー式クラッチの調整方法を解説します。
クラッチを握りやすくして運転を楽にしたい方は、ぜひ最後まで読んでいってくださいね。
ステップ①:レバー側のロックナットとアジャスターを調整する
ここでは、レバー側のロックナットとアジャスターでクラッチの調整をする方法を紹介します。
クラッチレバーの根元を確認する
ハンドルの左側にあるクラッチレバーの根元には、ロックナットとアジャスターが取り付けられており、クラッチの調整が可能です。
一部車種には保護用のゴムブーツが付いているものもあります。まずは、自分のバイクのクラッチレバーの根元を確認し、ゴムブーツがある場合は外しましょう。
ロックナットを緩める
まず、ロックナットを緩めます。
アジャスターとロックナットが固着して一緒に回ることがあるため、アジャスターをしっかり固定し、ロックナットだけを緩めるようにしてください。
手でも回せるようになっている場合もありますが、パンチなどの工具で固く締められているケースもあるため、必要に応じて工具を使いましょう。
アジャスターを回して調整する
ロックナットを緩めたら、アジャスターを回してクラッチの遊びを調整します。
アジャスターをクラッチホルダー側に締め込むと遊びが大きくなり、逆に緩めると遊びが小さくなります。
レバー先端が1~2cmほど軽く動く程度に調整するのが理想です。
アジャスターを緩めすぎると外れる危険があるので注意してください。
一部車種はダイヤルでも調整できる
一部のバイクには、ロックナットやアジャスターに加え、レバーの根元にダイヤルが装備されています。
そのような車種では、まずダイヤルで大まかに調整し、不足する分をアジャスターで補うとよいでしょう。
ダイヤルには数字が書かれているため微調整は難しいですが、アジャスターを回すより手軽に行えます。
ブレンボなどの社外クラッチレバーの場合、数字の代わりに調整ノブが付いているので、無段階で調整可能です。
ステップ②:クラッチ側のワイヤーを調整する
ここでは、クラッチ側のワイヤーを調整する方法を紹介します。
エンジンのクラッチ側にも調整ナットがある
クラッチワイヤーを下へたどっていくと、ワイヤー後端の少し手前にステーがあり、ナットで挟まれている部分があります。
エンジンのクラッチ側での調整は、このステー部分で行うことが可能です。
両側のナットを緩める
ナットはステーを挟んで両側に付いています。
スパナを2本使って、互いのナットを供回りしないように緩めましょう。
1本だけで回そうとすると反対側が供回りしてしまい、緩まないので注意してください。
ナットを回しながら調整
ナットを回しつつ、時々クラッチレバーを握って調整しましょう。
エンジン側のナットをステー側に締め込むとクラッチワイヤーが緩み、逆に緩めると引っ張られるため遊びが小さくなります。
反対側のナットはエンジン側と逆方向に回すことで、ワイヤーの張りを一定に保ちます。
エンジン側を緩める場合は反対側を締め、エンジン側を締める場合は反対側を緩めるという手順です。
元の場所を覚えておく
エンジンのクラッチ側の調整を行う機会は少なく、クラッチワイヤー交換時などに触れる箇所です。
調整を誤るとクラッチが切れなかったり、滑りの原因になる場合もあります。
調整前には、元の位置をマーキングするか写真を撮っておき、いつでも戻せるようにしましょう。
ステップ③:クラッチレバーの位置を調整する
ここでは、クラッチレバーの高さを調整する方法を紹介します。
クラッチレバーの場所を変更する
クラッチを調整してもまだしっくりこない場合は、クラッチレバー自体の高さを変更してみましょう。
クラッチホルダーの固定ボルトを緩める
クラッチレバーを保持しているクラッチホルダーは、ボルト2本で固定されていることが多いです。
その2本を少しだけ緩めて、ホルダーが硬めに動く程度にします。
緩めすぎるとクラッチホルダーが一気に回転し、周囲に傷を付けるおそれがあるので注意しましょう。
クラッチホルダーを上下に動かす
ボルトを少し緩めたら、クラッチホルダーを上下に動かして高さを調整します。
身長が低い方はレバーを下側にセットし、高い方は上側にセットすると操作しやすいです。
腕や手首の角度を考慮し、無理なく握れる位置に合わせましょう。
フロントブレーキ側の高さも調整する
クラッチレバーと同様に、右側のブレーキレバーも高さを調整できます。
ブレーキホースやアクセルワイヤーとの干渉がないか、スムーズに動くかを確認しながら位置を調整しましょう。
新車時はメーカーの規定に合わせてある
新車の場合、万人向けの位置に調整されています。
そのため、納車時には、販売店で好みの高さに調整してもらうことをオススメします。
元の場所を覚えておく
クラッチレバーの高さを変える前には、いつでも戻せるようにマーキングをしたり、写真を撮っておきましょう。
純正ハンドルにはポンチマークが打たれており、その位置にホルダーやブレーキマスターシリンダーを合わせる場合が多いです。
ハンドルを社外品に交換しているなら、マジックなどで目印をつけておくと便利です。
ステップ④:実際に握ってみて、遊びや半クラッチの位置を確認する
ここでは、クラッチレバーを握って遊びや半クラッチの位置を確認する方法を紹介します。
クラッチレバーを握って遊びの確認をする
実際にクラッチレバーを握り、遊びの量をチェックしましょう。
遊びとは、クラッチが効き始めるまでの動作しない範囲のことで、適切な遊びがないと正しくクラッチを切れなくなります。
遊びが小さすぎるとギヤが入りにくくなったり、半クラッチ状態が続いてクラッチを痛めることにつながります。
一方で遊びが大きすぎると、ギヤを入れると同時にバイクが動き出してしまうなど、思わぬトラブルを招きかねません。
クラッチの遊びの調整
クラッチの遊びは、これまで紹介したアジャスターやエンジン側ナットの調整で行います。
メーカーによって異なりますが、1~2cmの遊びを基準としているケースが多いです。
もし、この範囲から外れるようならワイヤーの伸びや摩耗、あるいはクラッチ側の再調整が必要な場合があります。
調整後は実際にエンジンをかけ、1速に入れてゆっくりと半クラッチを試してみましょう。
定期的にクラッチの遊びの確認をする
大型バイクの一部は油圧式クラッチを採用しており、自動調整されるため遊びの確認は不要です。
しかし、ワイヤー式クラッチでは、使用しているうちに徐々にワイヤーが伸びるため、定期的なチェックが必要になります。
エンジンをかける前にレバーを握って遊びを確かめ、走行前にもエンジンをかけた状態で半クラッチの具合を確認してください。
まとめ
いかがだったでしょうか。今回はバイクのクラッチ調整方法を紹介しました。
多くのバイクはクラッチワイヤーで動作しており、使用を続けるうちにワイヤーが伸びて半クラッチの位置が変わり、切れにくくなるケースもあります。
販売店に依頼するのも良いですが、自分で調整できるようになると、待ち時間なく好きなときにクラッチの微調整が可能です。
今回紹介した方法と注意点を踏まえて、快適な運転のためにクラッチをしっかり調整していきましょう。
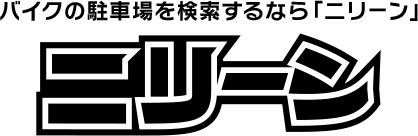



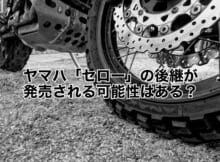

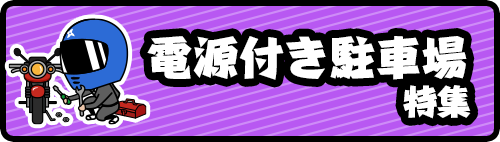
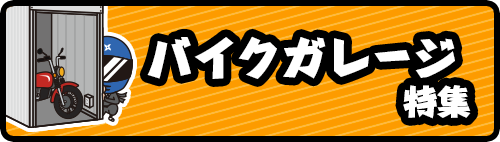
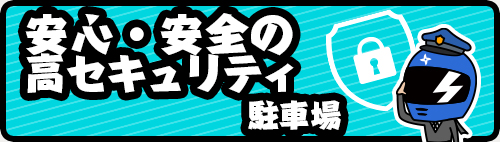
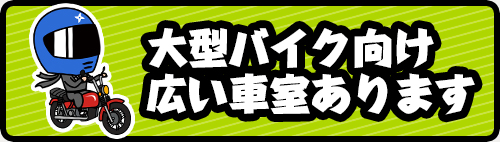
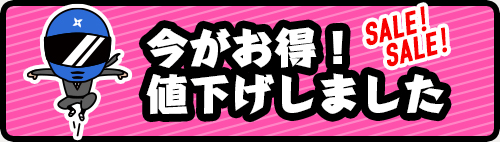

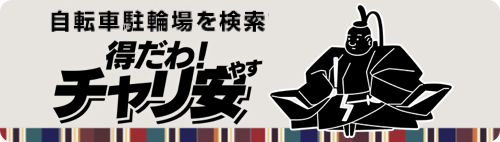

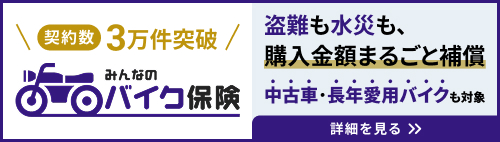

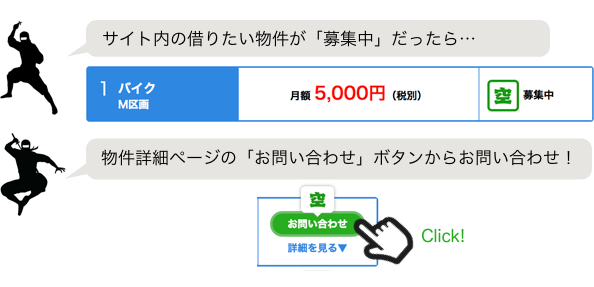
.jpg)