「バイク趣味はやめとけ」と周囲に言われた……やめるべき?
他の趣味とは少し毛色の違う、バイク趣味。
危険なのは承知の上で、楽しんでいる方はたくさんいらっしゃると思います。
ですが、バイク趣味を始めようとするときや、続けているうちに「やめておきなよ」と言われることもあるのではないでしょうか。
そこで今回は、「バイク趣味はやめとけ」と言われる理由と、バイク趣味を安全に楽しむための3つの方法を解説します。
「バイク趣味はやめておいた方が……」と言う方の気持ちも理解しつつ、折り合いをつけてバイク趣味を楽しめるよう気を配り、バランスの取れたバイクライフを目指しましょう。
目次
「バイク趣味はやめとけ」と言われる理由
ここでは、バイク趣味をやめたほうがいいといわれる理由について、いくつか紹介します。
事故の際のリスクが高い
バイクは車と違って身体がむき出しになっている乗り物です。
大きなフレームに守られている車と同じような事故をしても、バイクであれば受けるダメージはかなり大きくなります。
衝突や転倒などの事故の大小によっては障害が残ってしまったり、重大なケガに繋がったりする恐れがあり、事故の際のリスクがかなり高くなっています。
バイク趣味はお金がかかる
バイク趣味には想像以上にお金がかかります。
免許費用は車の免許を持っている人でも十数万円はかかります。
その上バイク代も高騰してきています。排気量や車種によっては車に匹敵する金額が必要になるケースも少なくありません。
また、車と大きく違うところは、安全装備への追加投資が不可欠な点です。
ヘルメットやジャケット、ズボン、プロテクターなど身を守るための装備が必須となります。
特に安全性を重視した高品質な商品を選ぶと、それだけで十数万円になることもあります。
加えて、定期的なオイル交換やタイヤ交換などのメンテナンス費用も、車に比べて頻度が高く、距離あたりのコストで考えると実質的に割高になることが一般的です。
身近な人からの切実な心配
家族からの反対を受けることもあるでしょう。
バイク趣味は、命に関わる危険を伴うため、家庭を持つ人にとって最愛の家族からの心配や懸念は乗り越えるのが最も難しいハードルかもしれません。
自分の身を案じて、バイクに乗るのをやめてほしいという切実な意見は、純粋な愛情から発せられているだけに重みがあります。
このように、バイク趣味が「やめた方がいい」と言われる背景には、単なる偏見ではなく、現実的なリスクへの認識があります。
反対意見にはバイクに対する愛情と同じくらい、乗る人の身を案じる気持ちが込められていることが多いのも事実です。
その気持ちを理解し、「だからこそ安全に楽しむ!」というスタンスを持つことが、バイク趣味を続ける上での重要な心構えと言えるでしょう。
バイク趣味を安全に楽しむ方法①:プロテクターをつける
ここでは、バイク趣味を安全に楽しむためのプロテクターについて紹介します。
プロテクターの役割
プロテクターはバイクに乗る上で重要なものです。
バイクという乗り物では、ライダーの身体が外部環境に直接さらされた状態で走行することになります。
そのような状態で転倒や事故が起きると、大怪我をしてしまいます。
こうした致命的な怪我から自分の身を守るために、プロテクターの着用は必須です。
事故時の衝撃を受けやすい部位
最も衝撃を受けやすいのは頭部で、次いで胸部や背中といった体幹部に強い衝撃が集中する傾向にあります。
頭部についてはヘルメット着用が義務付けられていますが、他の部位の防護対策は残念ながら重視されていないケースも少なくありません。
現在市販されているバイク用ジャケットの多くは、肘、肩、背中の三か所にプロテクターが標準装備されています。
ハイグレードのジャケットでは、高品質素材のプロテクターが採用されていたり、胸部プロテクターが追加装備されていたりします。
特に胸部プロテクターは、事故時の生存率に直接影響する重要な装備です。
標準で搭載されていないジャケットの場合は、別途購入してでも必ず装着しましょう。
スタイリッシュなプロテクターがある
プロテクターといえば、教習所で着用するようなロボットのようなもので、ダサいものだとイメージしている人が多いです。
しかし最近では、厳しい試験に合格し高い安全基準をクリアしながらも、驚くほど薄く軽量化されたモデルや、ジャケットのデザインに巧みに融合された一体型タイプのものもあります。
このようなタイプであれば、日常着感覚で違和感なくプロテクターを全身に身に着けることができます。
このように現代のプロテクターは、安全性を犠牲にすることなくスタイリッシュに進化しており、「安全か見た目か」という二択に迫られることは少なくなっています。
ファッション性を保ちながらも、特に生存率に直結する胸部や背中部分を防護することができるようになっているのです。
バイク趣味を安全に楽しむ方法②:安全運転を心がける
ここでは、バイク趣味を安全に楽しむための運転方法について紹介します。
かもしれない運転を心がける
バイクは爽快な走行感覚をもたらす反面、わずかな判断ミスが命取りになりかねない繊細な乗り物です。
走行中、簡単に事故や転倒につながる危険性があります。
このためバイク運転では、車以上に周囲の状況を広く把握し、常に先読みする意識が不可欠です。
左右の確認や前後の交通状況の確認は車と同じく必要ですが、車と違い、急ブレーキをしても短い距離ですぐに止まることはできません。
そのため、狭い道や横断歩道の前、カーブの前後などでは、横から車や人、自転車などが飛び出してくるかもしれないと常に先を見通した安全運転を心がけましょう。
大きな車の死角に入らない
バイクは小さな乗り物なので車の死角に入りやすいです。
車のドライバーは、ミラーである程度後ろの状況は見れますが、見えない領域が必ず存在し、その範囲に入ったバイクは完全に視認できなくなります。
こうした死角エリアに位置しているときに車両が進路変更や右左折を行うと、バイクはその意図を認識できないまま危険な巻き込み事故の犠牲になりかねません。
特に大型トラックやバスといった車両の死角は非常に広範囲に及び、ひとたび巻き込まれれば致命的な事故になる確率が高いため、死角ゾーンには絶対に留まらない運転を心がけることが重要です。
スピードを出し過ぎない
スピードは制限速度を守って運転することが重要です。
道路毎に標識で制限速度が表示されていますので、それを守って安全運転を心がけましょう。
天候や路面状況、交通量によっては制限速度よりも遅いスピードで走行することも必要です。
バイク趣味を安全に楽しむ方法③:定期的なメンテナンスを怠らない
ここでは、定期的なメンテナンスの必要性について紹介します。
運行前の日常点検
バイクの運行前には、下記のような日常点検が必要です。
①前後ブレーキの遊び・効き具合・ブレーキパッドの残量
②ブレーキフルードの量
③エンジンオイルの量・色
④灯火類(ヘッドライトやウィンカー)の確認
⑤タイヤの空気圧・溝
⑥冷却水(水冷式のバイク)の量
⑦エンジンのかかり具合
⑧低速・加速の状態
⑨その他異常箇所の確認
こうした基本的な点検を怠ると、走行中の突然の故障や機能停止によって、転倒事故を招いたり、交通の流れを妨げたりと、自分だけでなく他の道路利用者にも危険を及ぼす可能性があります。
どれほど優れたライディングスキルを持っていても、コンディションが不良なバイクでは安全性を確保することは不可能です。
バイクの運行前に日常点検を実施することで事故防止に努めましょう。
日常点検で異常を見つけても、自分で修理や調整ができない場合はバイク屋さんで整備をしてもらうようにしましょう。
見落としがちなチェーンメンテナンス
基本的な日常点検に加えて、特に注意を払うべき重要項目として、各メーカーが定期点検で指定しているドライブチェーンの状態確認があります。
チェーンは定期的に清掃・給油・調整をしなければ、運転中のバイクがギクシャクしたり、最悪チェーンが外れたり、切れたりしてしまいます。
チェーントラブルの危険性は想像以上に高いです。
走行中に外れたチェーンが周囲の車両に飛散して二次的な事故を招いたり、リアホイールをロックさせて転倒を引き起こしたり、切断時の反動で自身に致命的な怪我を負わせたりする可能性があります。
そのため、入念な点検と適切なメンテナンスは欠かせません。
日常点検で異常発見した際と同様に、自分で調整や修理ができない場合はバイク屋さんに点検してもらいましょう。
バイク屋さんで定期点検をしっかり実施する
バイクは車と同様に定期点検が必要です。定期点検は法定点検と言われています。
バイクは12ヵ月、24ヵ月に1回の点検が必要です。12ヵ月点検では33項目、24ヵ月点検では51項目の点検項目があります。
こうした定期点検の最大の価値は、日常点検では発見できない潜在的な故障箇所や消耗部品の劣化を早期に発見・対処できる点です。
結果として、予期せぬトラブルや事故リスクを大幅に軽減できます。
251cc以上のバイクは強制的に定期点検の機会が2年ごとにありますが、それ未満の小排気量バイクは車検がないため、点検整備が所有者の自主性に委ねられています。
そのため、愛車の点検をバイク屋さんに1回も出していないという人も多いです。
快適で気軽に走れる250cc以下のバイクに乗っているライダーは車検がない分、定期点検を自主的に行うようにしましょう。
愛車の寿命を延ばすだけでなく、ライダー自身の命を守る最も基本的な安全への投資です。
1〜2年に一度の点検費用は、予期せぬ重大事故のリスクと比較すれば、決して高すぎる出費ではありません。
このように、バイクを常に万全な状態で走らせるためには、定期的な点検が欠かせません。
そして、プロによる定期点検と並んで重要なのが、毎回の走行前に自分で行う日常点検であり、これを習慣化することです。
もっとも、特に初心者ライダーにとって「日常点検」と言われても具体的にどの部分を、どのように確認すべきか戸惑うこともあると思います。
そのような場合は、バイクを購入したお店や定期点検に預けているお店に日常点検について聞いてみましょう。
愛車に合わせた具体的な日常点検のポイントやコツを丁寧にアドバイスしてくれるはずです。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回はバイクの趣味を安全に楽しむ方法を紹介しました。
バイクは、跨ってエンジンをかけるだけでどこまでも行けそうな気持ちになる魅力的な乗り物です。
しかし、周囲からは「危険だからやめておけ」という声をよく耳にしているライダーの方が多いのも事実です。
今回紹介したバイクの趣味を安全に楽しむ方法を理解して、周囲の声にもしっかりと耳を傾けながら、安全に気を付けてバランスの取れたバイクライフを楽しみましょう。
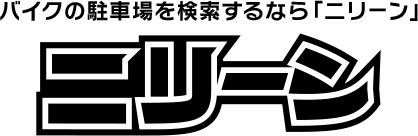

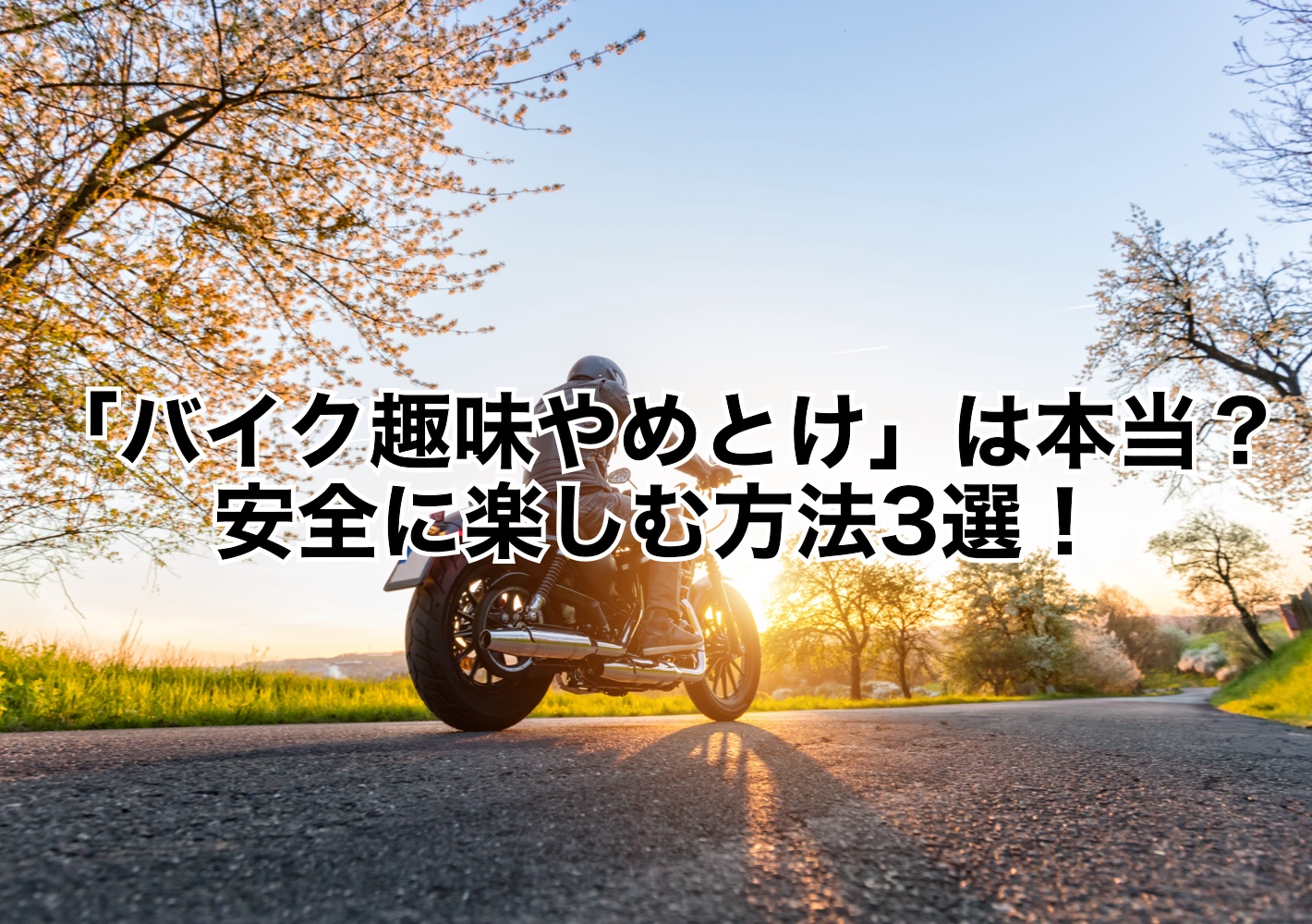



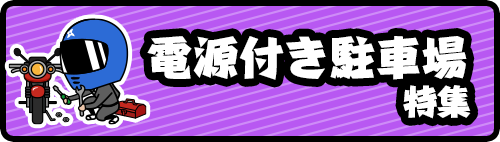
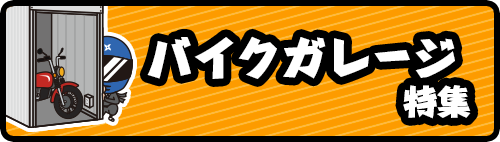
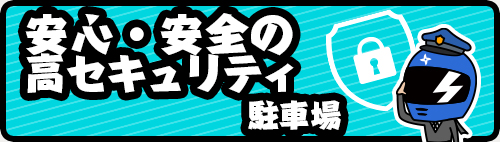
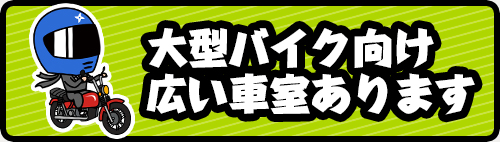
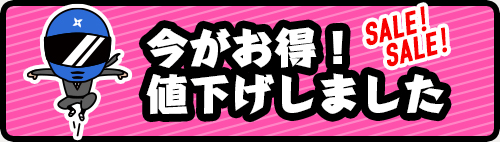

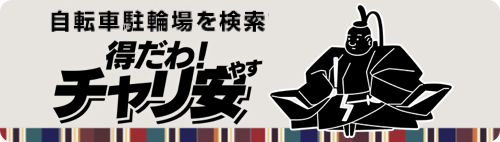

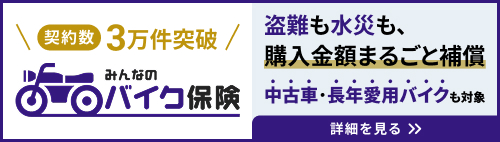

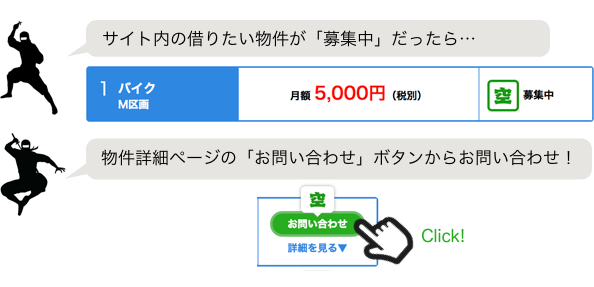
.jpg)