バイクチェーンが錆びている……これって自分でキレイにできる?
気づかないうちに付いてしまったバイクのチェーンの錆。
錆びたチェーンを見ると、「自分でなんとかできるのだろうか」と不安になる方もいるかもしれません。
しかし、ご安心ください。
手順を守って丁寧に清掃すれば、チェーンの錆は自分で落とすことが可能です。
そこで今回は、バイクチェーンの錆の落とし方について解説します。
初心者の方でも取り組めるよう、順を追って説明しますので、ぜひ最後までご覧いただき、愛車のお手入れに役立ててみてくださいね。
目次
錆を落とす手順①:チェーン専用のクリーナーを選ぶ
ここでは、チェーン専用クリーナーの選び方について紹介します。
チェーンは定期的なメンテナンスが必要
バイクのチェーンは、適度な油分を保ちながらエンジンの力を後輪に伝える重要な部品です。
チェーンは定期的にメンテナンスを行わないと、乾燥したり水分によって錆びたりするおそれがあります。
一般的には、走行500〜1000kmごとや雨天走行の後には、チェーンのメンテナンスを行うようにしましょう。
チェーン専用のクリーナーを使用する
パーツクリーナーは油汚れを落とすためのケミカル製品ですが、すべての種類がチェーンに適しているわけではありません。
チェーンを傷めないようにするためには、通常のパーツクリーナーではなく、チェーン専用のクリーナーを使用することをオススメします。
シールチェーン対応のものを選ぶ
バイク用品店や通販サイトでチェーンクリーナーを探すと、シールチェーン対応と記載されたスプレーを多く見かけます。
シールチェーンとは、チェーンの種類の一つです。
バイクのチェーンには、50〜125ccの原付や旧車など一部の車種を除き、ジョイント部分にOリングが取り付けられています。
このOリングの内部にはチェーンオイルが封入されており、この構造を持つチェーンをシールチェーンと呼びます。
シールチェーン専用と記載されていないパーツクリーナーで清掃や錆落としを行うと、Oリングを傷めたり、消耗を早めるでしょう。
そのため、チェーンの清掃や錆落としを行う際は、チェーン専用クリーナーであることに加え、シールチェーン対応かどうかも必ず確認してください。
錆を落とす手順②:チェーンにクリーナーを吹き付ける
ここでは、チェーンクリーナーをチェーンに吹き付ける手順について紹介します。
リヤタイヤを浮かせる
チェーンクリーナーを吹き付ける際は、効率よく作業を進めるために後輪を浮かせるのが望ましいです。
後輪を浮かせる方法にはいくつかあり、例えばレーシングスタンドやリアスタンドでスイングアームを支持する方法があります。
ただし、これらはスタンド操作とバイクの保持を同時に行う必要があり、1人で作業するには難しく、転倒のリスクも伴います。
一時的に手伝ってくれる人がいれば、作業の自由度が増すため、この方法はオススメです。
一方、1人で作業する場合には、サイドスタンドを使ったまま右側のスイングアームを持ち上げる方法があります。
チェーン清掃には十分な高さが確保できるため、この方法も有効です。
エンジンはかけない
チェーンに触れる作業では、必ずバイクのエンジンを停止し、誤って始動しないよう鍵を抜いておきましょう。
クリーナーを吹き付ける際は、チェーンを手で回しながら行います。
バイクの構造を理解してくると、エンジンをかけて1速に入れ、自動でチェーンを回したほうが効率的ではないかと思うかもしれません。
しかし、この方法ではチェーンに手が挟まれたまま巻き込まれてしまい、大けがを負うおそれがあります。
安全を最優先し、必ず手でタイヤを回すようにしてください。
また、手で回している最中でも、スプロケットに指が軽く挟まることがあります。
作業時は常に注意を払い、やさしくタイヤを回しましょう。
チェーンクリーナーが飛ぶ場所に養生する
チェーンクリーナーを使用すると液が周囲に飛び散るため、作業前に段ボールなどで周囲をしっかりと養生しましょう。
チェーン周辺には、ホイールやリヤサスペンションの付け根、サイドスタンドなどがあります。
これらにクリーナーが付着すると、細部まで洗浄しにくくなったり、放置によってシミになることがあります。
余計な手間を防ぐためにも、吹き付ける前にチェーン周りの保護を徹底することが大切です。
このように、まずは後輪を浮かせて作業しやすい環境を整えることが重要です。
そして、チェーン周りを触る際には、必ずエンジンを停止し、鍵を抜いたうえで、安全に作業を行いましょう。
錆を落とす手順③:チェーンをブラシでこする
ここでは、チェーンをブラシでこする手順について紹介します。
ナイロンブラシでこする
チェーンの錆を落とす際は、柔らかいナイロンブラシを使用するのが基本です。
錆を落としたいからといって金属製のブラシを使うと、前項で紹介したOリングを傷つけたり、破損させる原因になります。
そのため、Oリングを傷めないナイロンブラシを使用しましょう。
バイク用品店では、3面にブラシが付いたチェーン専用ブラシが販売されており、一度に広い範囲を清掃できるため便利です。
また、不用になった歯ブラシでも代用可能です。
手元に使い古した歯ブラシがあれば、活用してみてください。
プレート表面の錆は金属製ブラシでこする
スプロケットとチェーンの接触面にはOリングがあるため、金属製ブラシの使用は避ける必要があります。
しかし、プレートの表面や裏側に錆が多く見られる場合は、金属製ブラシを使用しても問題ありません。
その際は、Oリングに触れないよう細心の注意を払いましょう。
プレート表面は比較的傷つきにくいものの、ステンレス製など硬い材質のブラシで強くこすると傷がつく可能性があるため、力加減にも注意が必要です。
クリーナーが乾く前にこする
チェーンをこする際は、クリーナーが乾燥しないうちに作業を行うことが重要です。
乾燥すると清掃に時間がかかるだけでなく、やさしくこすっているつもりでも表面に傷がついてしまうことがあります。
クリーナーの状態をこまめに確認しながら、丁寧に作業を進めてください。
このように、チェーンの錆を落とすには、Oリング部分にはナイロン製の柔らかいブラシ、プレート部分には金属製ブラシを使い分けるのが基本です。
また、作業時には汚れやクリーナーの飛散を防ぐため、周囲をしっかり養生してから始めましょう。
錆を落とす手順④:ウエスで錆を拭き取る
ここでは、落とした錆や汚れをウエスで拭き取る手順について紹介します。
錆が落ちたら拭き取る
錆や汚れが落ちてきたら、早めにウエスで拭き取りましょう。
クリーナーが乾燥しないうちに拭き取ることで、仕上がりがきれいになります。
拭き取る際は、ゴシゴシと強くこするのではなく、やさしく丁寧に行うことが大切です。
また、薄手のウエスはチェーンに引っかかって破れやすく、手を傷つける可能性があります。
ある程度厚みのあるウエスを使うことで、怪我のリスクを減らすことができます。
使い捨てのウエスが便利
チェーンに付着した汚れや錆は頑固なため、一度使ったウエスをきれいに洗うのは困難です。
そのため、ウエスは再利用せず、使い捨てのものを使用するのが効率的です。
使い捨てウエスを使用すれば、短時間で手軽にチェーンを清掃することができます。
体に汚れが付着すると落ちにくい
チェーン清掃中に体に汚れが飛び散ると、付着した汚れはなかなか落ちません。
整備用の石けんを使っても完全には落としきれない場合があります。
作業時には、汚れても問題のない長袖の古着や作業服を着用し、衣服や肌を保護しましょう。
このように、チェーンの錆や汚れを拭き取る際には、ある程度厚みのあるウエスを使うことで手を守ることができます。
また、使い捨てのウエスや古着、古タオルなどを活用し、汚れたらすぐに処分することで、効率的に作業を進められます。
錆を落とす手順⑤:給油して錆を防止する
ここでは、仕上げとしてチェーンに給油する手順を紹介します。
チェーンクリーナーだけでは乾燥してしまう
錆や汚れをチェーンクリーナーで落とすと、見た目はきれいになりますが、チェーンが乾燥してカサついた状態になります。
このままバイクを走行させると、チェーンが摩耗して伸びやすくなり、短時間で錆が再発する可能性もあります。
そのため、クリーニング後にはチェーンルブを給油することが欠かせません。
錆や汚れの拭き取り後は数分待つ
チェーンクリーナーで錆や汚れを落としたら、できるだけ丁寧に拭き取りましょう。
その後は、クリーナーが完全に乾くまで数分間待機します。
クリーナーが残った状態ではチェーンルブが定着しにくいため、乾いてから給油するのが理想です。
チェーンルブを給油する
チェーンルブを給油する際は、注油する箇所に注意が必要です。
まずは、シールチェーンのOリング部分に給油します。
Oリングはチェーンの手前側と裏側の両方にあるため、どちらにも均等に注油してください。
続いて、スプロケットと接触するローラー部分にも給油します。
最後に、錆びやすいプレート部分にも忘れずに注油しましょう。
余分なチェーンルブをウエスで拭き取る
給油が終わったら、チェーン全体を観察し、余分なチェーンルブが残っていないかを確認します。
そのまま走行すると、リアホイールやフェンダーにチェーンルブが飛び散る原因になります。
これを防ぐために、ウエスをチェーンに軽く当て、余分なチェーンルブをやさしく拭き取りましょう。
拭き取りすぎないよう、適度な力加減を意識することが大切です。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は、チェーンについた錆の落とし方について紹介しました。
バイクは新車のうちはチェーンもきれいですが、走行を重ねるうちに徐々に錆や汚れが目立つようになります。
今回紹介した手順を参考に、ぜひチェーンメンテナンスに挑戦してみてください。
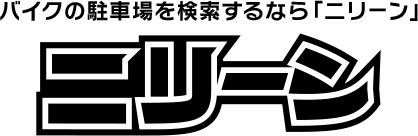





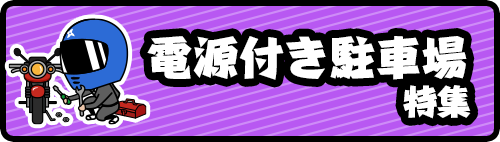
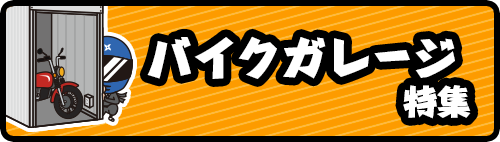
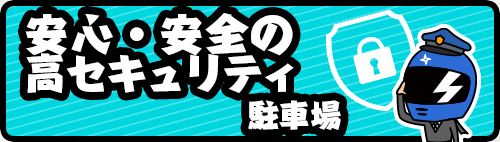
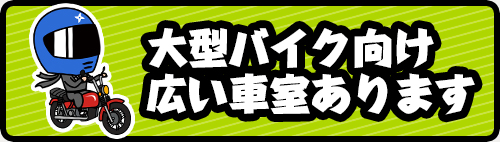
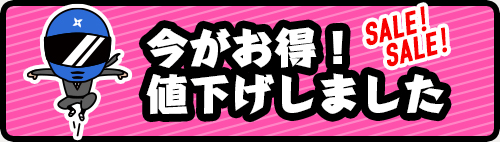
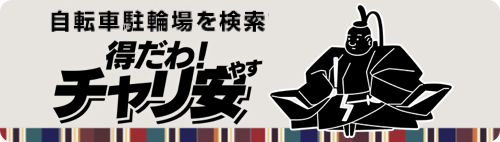


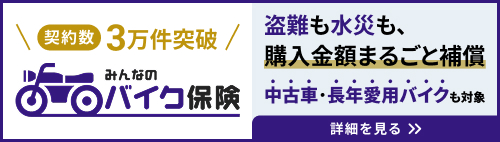

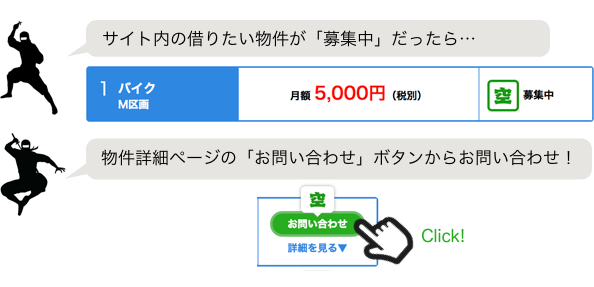
.jpg)