バイクのタイヤを交換したい!自分でできる?
サーキット走行やレースを始めると、タイヤの摩耗が気になってきます。
「毎回ショップで交換してもらっているけど、費用や手間が負担に感じる」という方も多いのではないでしょうか。
そこで次に考えるのが「自分で交換できないか」ですよね。
ということで今回は、バイクのタイヤを自分で交換する方法について解説します。
必要な道具があれば自分で交換するのも不可能ではありません。
興味がある方は最後まで読んでいってください。
ステップ①:タイヤ交換に必要な道具を揃える
ここでは、バイクのタイヤ交換に必要な道具について紹介します。
フロント・リアスタンド
バイクからホイールを外すためには、バイクを浮かせないといけません。
そこで役立つのがフロント・リアスタンドです。
リアスタンドには様々な種類があるため、ミニバイクや中型サイズのバイク、大型バイクのサイズに合わせたものを用意しましょう。
テコの原理でバイクを持ち上げるので、少ない力で持ち上げられるロングタイプは効率的です。
また、バイクのスイングアームには、スタンドを引っ掛けるためのボルトフックを取り付けられるネジ穴が開いていることがあります。
この穴がある場合には、フックボルトを取り付けてスタンドを使いやすくするのがオススメです。
フロントスタンドにも様々な種類があるため、足回りの仕様にあわせて用意しておきましょう。
なお、スクーターはセンタースタンドが装備されているため、リアタイヤはそのまま簡単に取り外せます。
フロントを持ち上げる際はジャッキを使用するため、スクーターに乗っている方はフロントジャッキを用意しましょう。
メガネレンチやボックスレンチなどの工具
バイクからタイヤを取り外すには専用工具が必要です。
必要な工具はバイクによって異なりますが、多くの場合8~24mmのメガネレンチのセットやボックスレンチのセットがあれば、ブレーキキャリパーの取り外しとホイールの着脱が可能です。
また、タイヤの空気を抜くために必要なムシ回しも用意しましょう。ムシは特殊な形状のため、専用のムシ回しが必要になります。
タイヤレバー
タイヤレバーは、ホイールからタイヤを取り外すために必要な工具です。しかし、タイヤレバー1本でタイヤを外すことはできません。
最低でも3本用意しておくと、スムーズにタイヤを取り外すことができるので、オススメです。
ビードブレーカー
ビードブレーカーは、タイヤをホイールのリム部分から落とすための工具です。
これがないとホイールとタイヤの間に隙間ができず、タイヤレバーを挿入することができません。
タイヤによっては手の力でビードを落とすことも可能ですが、ビードブレーカーがあると作業が格段にスムーズに進みます。
ビードワックス
ビードワックスは、タイヤのビード面に塗布してホイールへの取り付けを容易にする潤滑剤です。
これを使用することでビード面を傷つけることなく、タイヤを丁寧かつスムーズに装着できます。
さらに、ビード面からの空気漏れを防ぐ効果もあります。
ステップ②:タイヤをバイクから外す
道具がそろったら、バイクからタイヤを外しましょう。ここからは、その方法について解説します。
まずはボルト類を緩める
まずは、固く締まっているアクスルシャフトやシャフト固定のボルト、キャリパーボルトを緩めていきましょう。
スタンドで持ち上げた状態でボルトを緩めるとバイクが動き、スタンドが外れ、バイクが倒れてしまう危険性があります。
そのため、まずは車体を地面に接地させた状態でボルトを緩めてから、スタンドで持ち上げるようにしましょう。
キャリパーを外してホイールを外す
ブレーキキャリパーを取り外すと重みで垂れ下がり、ブレーキホースに負荷がかかってしまいます。
外したキャリパーはボルト穴に針金や紐を通し、スタンドに引っ掛けてブレーキホースを保護しましょう。
ブレーキキャリパーを外すと、ホイールとそれを固定するアクスルシャフトだけが残る状態になります。
ホイールの下に足を挟んでタイヤを保持することで、アクスルシャフトをスムーズに引き抜くことができます。
ホイールからカラーやメーターギヤを外す
外したホイールには、カラーやメーターギヤが装着されている場合があります。
そのまま放置すると、作業中にカラーやメーターギヤが落下して紛失する恐れがあるため、必ず取り外しておきましょう。
また、カラーなどのホイール付属部品は左右で厚みが異なる場合があるため、左右を間違えないよう注意して保管してください。
ステップ③:タイヤのビードをホイールから落とし、タイヤを外す
タイヤの空気を抜く
タイヤを寝かせて空気を抜きましょう。
ホイールを地面に直接置きたくない場合は、タイヤ部分に板を敷いてその上に置きます。
空気を抜くには、エアバルブのキャップを外した中にあるムシゴムを、ムシ回しを使って取り外し、空気を抜いてください。
空気は勢いよく抜けるため、ムシを紛失しないよう注意しましょう。
ビードブレーカーでビードを落とす
タイヤのリムとすぐ近くにビードブレーカーのツメをセットしてビードを落としていきましょう。
ホイールのリムから離れた位置にツメをセットすると、タイヤに上手く力が伝わらなかったり、ツメがタイヤから外れてしまったりすることがあるので、リムに近い場所にツメをかけてください。
エアバルブと反対側のビードを落とす
エアバルブ側でビードを落とすと、エアバルブにビードが引っかかってしまうので、上手く落ちない場合があります。
特に、社外品のエアバルブやアルミ製のエアバルブではビードが引っかかるだけでなく、エアバルブの破損に繋がることがあるので注意しましょう。
ビードを落とした後は、隣接する部分を順次押していくことで全周のビードが落ちていきます。
タイヤレバーでタイヤを外す
ビードを落としたら、タイヤレバーを使ってタイヤをホイールから取り外していきます。
1本目で持ち上げた状態をキープしながら、残りの2本で順次持ち上げていきましょう。
片側が外れたら、もう一方も同じ手順で外していきます。
タイヤレバーが接触する部分に傷が付く可能性があるため、リムガードを使用しながらレバーを操作しましょう。
ホイールとタイヤの回転方向を確認しておく
タイヤには決められた回転方向があります。タイヤを外す前に、必ず回転方向を確認しておきましょう。
また、ホイールにも回転方向が設定されている場合があるため、こちらも併せて確認が必要です。
回転方向を間違えると再度タイヤを脱着する羽目になるため、二度手間を防ぐためにも事前確認を怠らないようにしましょう。
ステップ④:新しいタイヤをホイールにはめる
タイヤ・ホイールにビードクリームを塗る
タイヤにビードクリームを塗りましょう。
ビード面やタイヤの内側に塗ることでタイヤが滑りやすくなり、スムーズに装着できるからです。
もし、効果が感じられない場合はホイール側にもビードクリームを塗ってみましょう。
外す時の逆の手順でタイヤをはめていく
タイヤレバーを使って、タイヤを片側ずつ装着していきます。
レバーで新品タイヤのビードを傷つけたり切ったりしないよう、細心の注意を払いながら慎重に作業を進めましょう。
タイヤの軽点を確認して空気を入れる
タイヤを両側とも装着したら、全周にわたってタイヤがホイールに正しく収まっているか確認しましょう。
タイヤには軽点を示す黄色や赤色のマークが付いています。
この軽点をホイール側で最も重いエアバルブの位置に合わせることで、タイヤとホイールのバランスが最適化されます。
空気を注入していくと徐々にビードが上がってきて、最終的に「パン」という音とともにビードが両側全周にわたって立ち上がります。
タイヤの空気圧をメーカー規定値や自分の好みに調整すれば、タイヤ交換の完了です。
ステップ⑤:ホイールを元の位置に戻す
回転方向、ビードが上がっているか確認する
タイヤ交換が完了したら、再度回転方向とビードが正しく上がっているかを確認しましょう。
さらに、ムシがしっかりと締まっているか、空気圧が規定値に設定されているかも併せて確認してください。
ホイールベアリングの確認、シャフト類へのグリスアップ
ホイールベアリングの確認は、アクスルシャフトを外してバイクからホイールを取り外した際のみ可能です。
ベアリングがスムーズに回転するかどうか、指で回してチェックしましょう。古いグリスが残っている場合は拭き取って清掃してください。
その後、アクスルシャフトに新しいグリスを塗布します。
また、ブレーキキャリパーのボルトには焼き付き防止用のグリスを塗っておきましょう。
なお、ブレーキを外している間は、絶対にブレーキレバーを握らないよう注意が必要です。
バイクにタイヤを付けて、各部締め付けていく
バイクにタイヤを取り付けていきます。
ホイールをアクスルシャフトに差す穴に合わせてからシャフトを差していきます。その際、差す方向を間違えないように注意してください。
ホイールを固定したら、ホイールがスムーズに回転するかを確認しましょう。
その後、アクスルシャフトの固定ボルト、ブレーキキャリパーのボルトを締め付けていきます。
締め付け後は、ブレーキが引きずっていないか、ホイールを回転させてブレーキの作動確認をしてください。
すべての作業が完了したら、バイクを前後に押し引きして異常がないという最終確認を行いましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は自分でバイクのタイヤを交換する方法を紹介しました。
スポーツ走行やサーキット走行の頻度が増えると、それに伴ってタイヤ交換の回数もかなり多くなります。
そんな時に自分でタイヤ交換ができれば便利だと感じる方も多いでしょう。
今回解説したタイヤ交換に必要な道具や手順を参考に、愛車のタイヤ交換にぜひ挑戦してみてください。
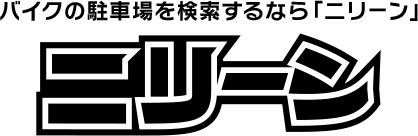





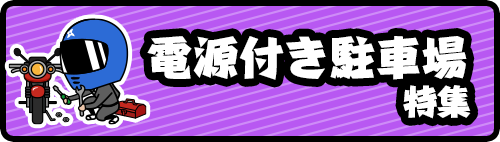
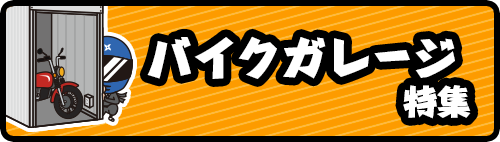
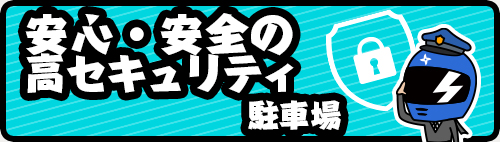
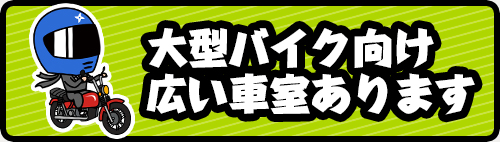
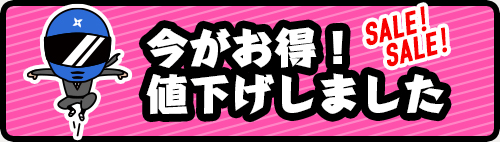

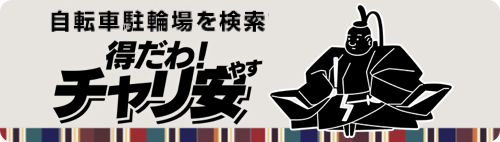

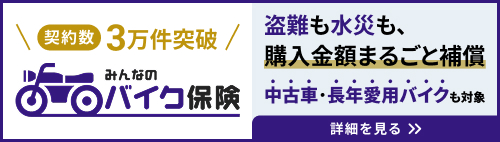

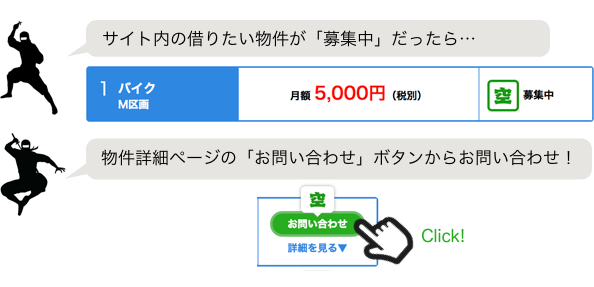
.jpg)