タイヤに空気入れが必要な理由
バイクを安全に楽しむために欠かせないのがタイヤの空気圧管理です。
普段はあまり気にしていなくても、空気が足りないだけで燃費や走り心地が悪くなり、最悪の場合は転倒や事故の原因にもなりかねません。
そこで今回は、バイクのタイヤに定期的な空気補充が必要な理由や正しい方法、さらにオススメの空気入れをまとめて紹介します。
この記事を読めば、初心者の方でも安心してタイヤのメンテナンスができるようになりますよ。
目次
タイヤへの正しい空気入れの方法とは?
正しい空気入れの手順を理解すれば、初心者でも安心してメンテナンスができます。
ここでは、正しい空気入れの方法を紹介します。
空気入れの方法①:規定空気圧を確認
まずは、バイクの規定空気圧を確認しましょう。
タイヤはバイクごとに異なっており、規定の空気圧もそれぞれ違います。
規定空気圧は取扱説明書に記載されていますが、多くの場合、チェーンカバーやスイングアーム付近に貼られたステッカーでも確認できます。
このステッカーには空気圧のほか、チェーンの遊び量なども記載されています。
空気入れの方法②:バルブキャップを外す
エアバルブのキャップを反時計回りに回して取り外します。
取り外したキャップは紛失しやすいため、ポケットなど安全な場所に保管してください。
バルブキャップは単なる飾りではなく、エアバルブ内への異物混入や空気漏れを防ぐ重要な部品です。
作業完了後は必ず元に戻しましょう。
空気入れの方法③:空気入れの先をしっかりと装着する
空気入れの先をエアバルブにしっかりと装着しましょう。
装着が浅い、または取り付けが斜めになっている場合には、隙間から空気が漏れてきたり、正しい空気圧がゲージに表示されたりといったことがあるので注意しましょう。
空気入れの方法④:少しずつ空気を入れる
空気は規定値まで一気に入れるのではなく、ゲージで空気圧を確認しながら調整して入れていきましょう。
空気入れの方法⑤:規定値まで入れたらバルブキャップを締める
規定値まで空気を入れたら、空気漏れがないかを確認してバルブキャップを締めます。
先述の通り、空気入れをしている最中にはバルブキャップがなくなってしまいやすいです。
しっかりと保管しておき、最後に必ずキャップをしましょう。
このような流れで空気入れをすることで、適切な空気圧を維持することができます。
定期的な空気圧チェックと補充を習慣化することが、安全なバイクライフの基本です。
タイヤへ空気を入れる際に注意することは?
タイヤの空気圧は簡単に調整できますが、いくつか注意するポイントがあります。
ここでは、空気を入れる際の注意点について紹介します。
注意点①:走行直後には測定しない
タイヤ内の空気は熱によって膨張します。
走行直後はタイヤが熱を持っているため、空気が膨張し、実際よりも高い空気圧が表示されます。
正確な測定と調整を行うため、空気圧チェックと補充は必ず走行前、またはタイヤが完全に冷えた状態で行ってください。
注意点②:前後輪の規定空気圧を守る
タイヤの空気圧は、バイクごとに異なるだけでなく、バイクのフロントとリアタイヤでも異なります。
多くのバイクは、リアタイヤの空気圧がフロントタイヤよりも高くなっています。
前後同じ空気圧にするのではなく、しっかり確認して補充しましょう。
注意点③:定期的に空気圧のチェックをする
タイヤの空気は、パンクしていなくても自然に少しずつ抜けていきます。
空気圧の点検は最低でも月に一度はするようにして、タイヤトラブルを未然に防ぎましょう。
注意点④:空気の入れすぎに注意
先述したように、タイヤの空気圧の点検は最低でも月に1度するのが目安です。その作業が面倒になってしまうこともあるでしょう。
しかし、点検頻度を減らそうとして規定値よりもさらに入れるのは危険です。
過剰な空気圧は乗り心地を悪化させるだけでなく、タイヤの接地面積が減少してグリップ力が低下し、転倒リスクが高まるからです。
注意点⑤:ゲージを確認する
空気圧を点検・補充するときには必ずゲージを確認しながら行うようにしましょう。
感覚や目視では正確な空気圧が確認できません。
数値を正確に把握するために、空気圧ゲージ付きの空気入れを使いましょう。
タイヤへの空気補充は簡単に見えて、実は多くの注意点があります。
誤った方法での作業は、空気漏れやタイヤ損傷の原因となり、最悪の場合は走行中のトラブルに繋がります。
自分の安全のため、一つ一つの手順を丁寧に確実に行うことが重要です。
バイクの空気入れを選ぶポイント
バイク用の空気入れには、いくつか種類があります。選ぶ基準を知っておくと、失敗を防ぐことができます。
ここでは、バイクの空気入れを選ぶポイントを紹介します。
ポイント①:ゲージ付き、バイク用のもの
バイクのタイヤに空気を入れるときには空気圧ゲージが必須です。
正確な数値を把握するために、空気入れについていることが多いですが、安価な商品にはついていないことがあったり、ゲージが正確でなかったりというケースもあります。
そのため、バイクの空気入れを選ぶときには、ゲージの有無や耐久性も考慮して、安価過ぎないバイク用の空気入れを選びましょう。
ポイント②:バルブ形状の確認
バイクのエアバルブには、ストレートタイプや曲がりタイプがあります。
空気入れによっては、形状に合わず空気を入れにくいものがあります。
そんなときには、先端のアタッチメントが交換できる空気入れを使うのも一つの選択肢です。
ちなみに、バイクや車のエアバルブは米式バルブです。
自転車用など、バイク専用でない商品を検討する際には米式バルブ対応のものを選びましょう。
ポイント③:持ち運びやすさを考える
バイクの空気入れを家で使うのか、ツーリング先で使うかどうかで最適な空気入れのサイズも変わってきます。
家で空気を入れるならサイズは関係なく、空気を入れやすいものがオススメです。
使いやすさと性能を優先しましょう。
もし、ツーリング先などの出先での使用を想定しているなら、携帯性を重視してコンパクトなものを選びましょう。
ポイント④:電動式と手動式
バイク用の空気入れには電動式と手動式があり、それぞれに特徴があります。
電動式は、コンパクトでバッグに入るサイズなので、携帯性に優れています。
また、手間もなくボタンを押すだけで空気を入れることができるので、体力を使いません。
利便性は高いですが、価格が高いのがネックです。
手動式は、電動式と比べて安価で機械的構造がシンプルなため、故障しにくく信頼性が高いのが特徴です。
ただし、高圧まで空気を入れるには相応の体力と時間が必要となります。
バイクの空気入れのおすすめ
ここでは、オススメのバイク用空気入れを紹介します。
南海部品 NP-D6 電動エアーポンプ
オススメポイント
南海部品の空気入れは電動です。
小さくて細いのでバッグに入れて、持ち運ぶことができます。
バッグやシート下に収納でき、日常のタイヤ空気圧点検からツーリング先でのトラブル対応まで幅広く活用できます。
操作は非常にシンプルで、目標空気圧を設定すれば自動的に空気を充填し、設定値まで達すると自動停止します。
また、バッテリーの残量表示、LEDライト、ボールや自転車用など各種アダプターがついているという実に多機能な空気入れです。
充電は、付属のUSBタイプCケーブルで2〜3時間で完了します。
連続稼働時間は15分と、ポケットサイズの製品としては長持ちです。
南海部品について
大阪にある南海部品は、バイク用の部品や用品、ウェアなど様々なものを開発・販売している老舗バイク用品メーカーです。
南海部品は1953年に設立されて以来、オリジナル商品から海外ブランド商品まで幅広く取り扱っています。
- 商品名:南海部品 NP-D6 電動エアーポンプ
- バッテリー:2000mAh
- 連続稼働時間:15分
- 充電時間:2~3時間
- 公式ホームページ:サイトはこちら
マキタ MP181D 充電式空気入れ
オススメポイント
マキタの充電式空気入れMP181Dは、最高圧力が1,110kPaまで対応可能なので、大型バイクやスポーツバイクなどの高い空気圧にも対応できます。
ちなみに、下位モデルにMP180Dがありますが、大型バイクの規定空気圧に届かない場合があります。
高速な充填ができるのも大きな特徴で、空気圧調整に時間をかけたくない人にオススメです。
目標空気圧の設定や、まとまりやすいホース、LEDライト、時計などの便利機能も満載で、かなり実用性が高いです。
携帯するには少し大きいので、自宅で使うのが最適です。
バッテリーは18Vで別売りとなっています。
マキタの電動工具をすでに持っている人は、そのまま装着できます。
マキタについて
愛知県にあるマキタは、日本を代表する電動工具メーカーです。
持続可能な社会に貢献しながら、工具を通して人の暮らしと住まい作りを支える”グローバルサプライヤー”として確固たる地位を築くことを目標とした、「Strong Company(強い会社)」の実現を目指しています。
- 商品名:MP181D 充電式空気入れ
- 電源:直流18V(バッテリー、充電器別売)
- 最高圧力:1,110kPa(11.1bar)
- 吐出量:22.0L/min(200kPa時)
- 公式ホームページ:サイトはこちら
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回はバイク用のオススメの空気入れを紹介しました。
バイクのタイヤは常に適正な空気圧を保つことで安全に乗ることができます。
正しい空気圧管理には、適切な手順を理解して、信頼できる道具を使うのが大事です。
今回紹介した空気入れの方法とオススメの空気入れを参考にして、信頼できる空気入れを手に入れてください。
そして、最低でも月1回の空気圧点検を習慣化することで、安全で快適なバイクライフを実現しましょう。
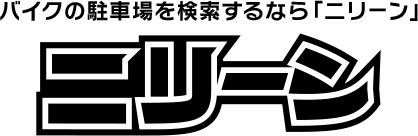





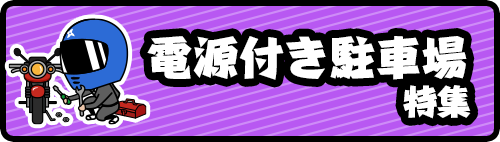
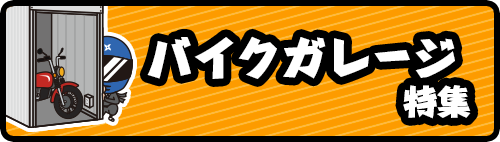
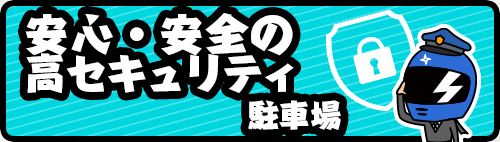
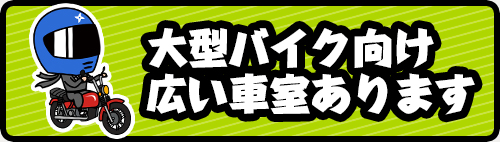
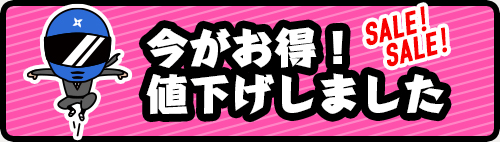
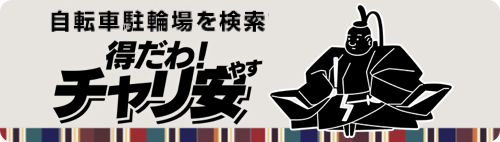


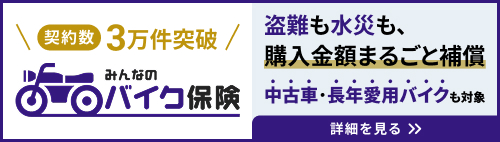

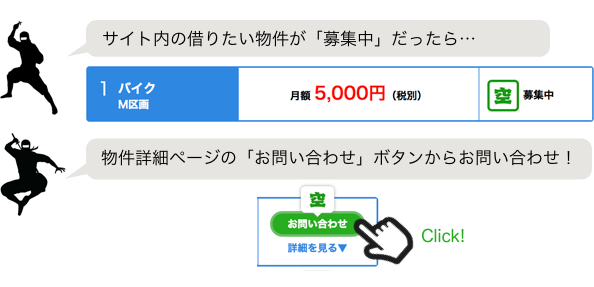
.jpg)